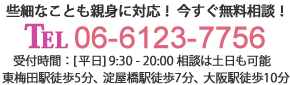保釈とは
刑事事件では、被疑者が逮捕された後に勾留が認められ、期限一杯まで勾留されたとしても、そこで不起訴になれば手続きは終了し、被疑者は釈放されて日常生活に戻れます。
しかしそこで起訴されてしまうと、起訴後勾留といってそのまま身柄拘束が継続されてしまい、さらに長期間の身柄拘束を受けることになってしまいます。
起訴後勾留では、裁判が終わるまで身体を拘束されています。そうすると、かなりの長期間、身体拘束が続くことになります。
証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがない被疑者にとっては、あまりに過酷なことですので、一定の手続きを踏んで身体拘束を一時的に解くことができます。これが保釈です。

保釈の種類・要件
保釈には、3種類のものがあります。
第1に、法の要件を満たす場合には、裁判所が保釈を認めなければならない「権利保釈」といわれるものがあります。以下の要件を全て満たす場合には、裁判所が保釈を認めなければなりません(刑事訴訟法89条)。
①被告人が死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではないとき
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがないとき
③被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではないとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がないとき
⑥被告人の氏名・住居が分かるとき
これらの要件をすべて満たす場合には、保釈がなされます
第2に「裁量保釈」があります。
これは、裁判所が、適当と認めるときは、職権で保釈を認めることができるというものです。
法律上は、はっきりした要件というものがあるわけではなく、被告人としては裁判所に保釈を認めるべきと考えてもらうことが必要になります。
その要素としては、被告人が逃走する可能性の有無、身元引受人の有無、就業や学業等に就かなければならないという保釈の必要性、予想される量刑(執行猶予がつくか実刑か)、否認か自白か、被告人の属性(反社会的勢力ではないか等)などがあります。
それらの点から、保釈が認められるべきであることを裁判所に対して主張することになります。
第3に「義務的保釈」といわれるものがあります。勾留があまりにも長くなり、不当な身体拘束といえるような状況になったときに、裁判所が保釈を行うというものです。実務上はほとんどありません。
保釈の手続き
まず弁護人としては、上で述べたどの類型の保釈に当たるかなどを判断し、家族や就業先等の協力も得ながら保釈請求の準備を行います。
準備が整えば、弁護人は、保釈請求書を裁判所に提出します。その際には、身元引受書や雇用主の陳述書などを添付資料として付けます。
保釈請求書を受領した裁判所は、内容を審査し、検察官の意見も聞いたうえで、場合によっては弁護人と面談するなどして、裁判官が、保釈するか否か、保釈するとして保釈金をいくらとするか判断を行います。
保釈が認められると、弁護人を通じて、保釈金を裁判所に納付し、納付したことが確認されると被告人が実際に保釈されます。
保釈金は、被告人が逃亡等をしなければ取り上げられること(「没取」といいます。)はなく、返却されます。金額はケースバイケースですが、保釈金を立て替えるなどの事業を行っている団体もありますので、多額の金銭が用意できない場合でもこれらの利用申し込みを行うことで、保釈金を用意できる可能性はあります。
保釈の効果
起訴後の勾留は、被告人が裁判を確実に受けるようにするために行われるものであり、保釈は、勾留されていなくても裁判を受けることを約束して釈放されるものです。
そのため、裁判で判決が出て、内容が実刑判決であった場合には、裁判を受け終わっており、なおかつ服役のために収監する必要がありますので、保釈の効力は無くなり、再び拘置所に収監されます。逆に、内容が執行猶予判決であった場合には、裁判を受け終わり、収監される必要もないので、保釈の効力は無くなりますが、判決を受け終わった後もそのまま家に帰ることができます。
いずれの場合でも、保釈の効果は終了していますので、保釈金の返還がなされます。
なお、実刑判決を受けて、それを不服として、控訴期間内に控訴する場合には、また保釈請求をすることになります。
被告人が保釈を希望している場合には、刑事弁護に強い弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。ご家族などが勾留されていて保釈を考えておられる場合には、ぜひご相談ください。